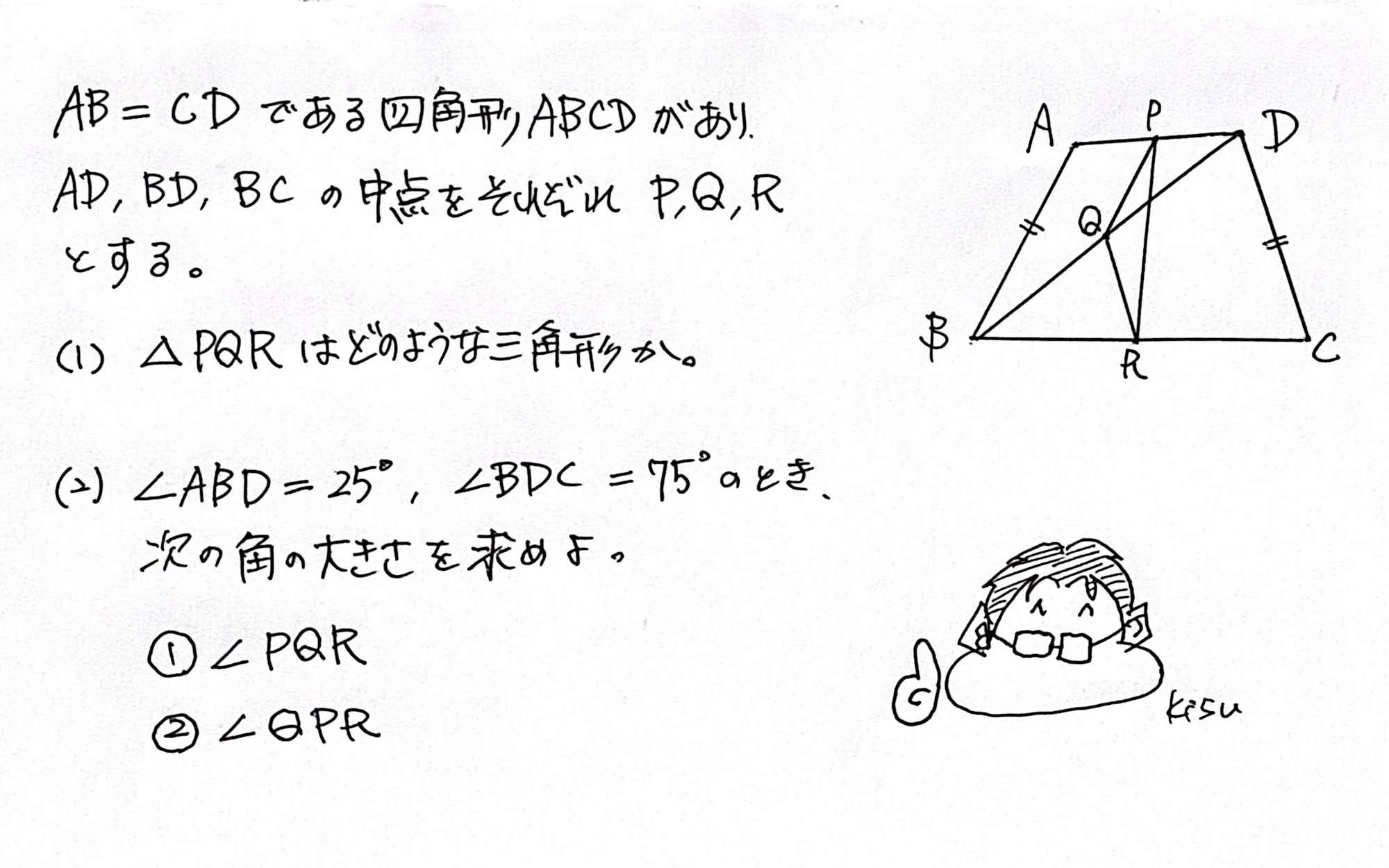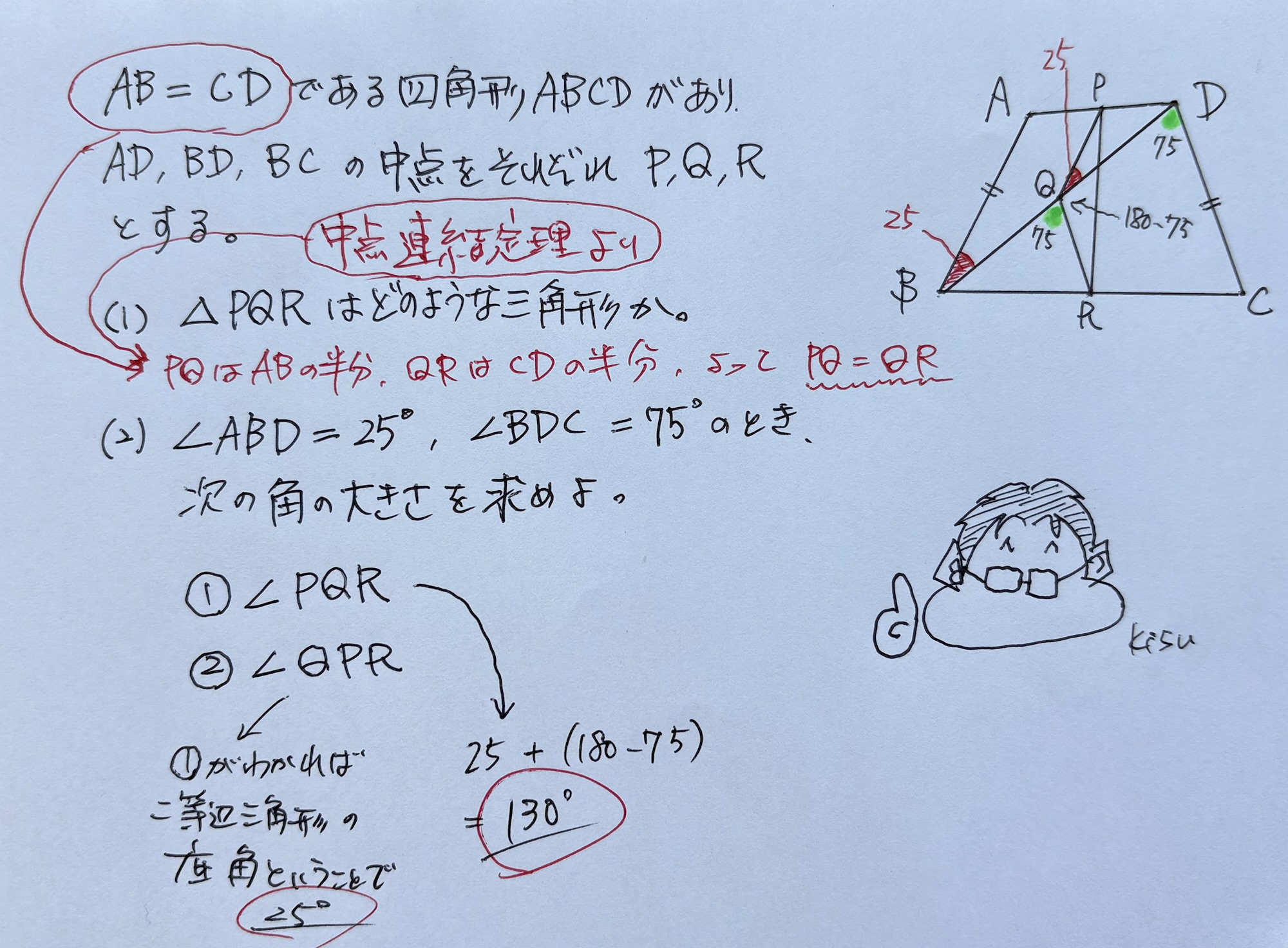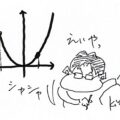気づくための手順
上の問題を考えてみよう。
中3の数学だ。
(1)は、ほとんどの人が見た目で二等辺三角形と答えるだろう。
何故かが説明できなくても二等辺三角形に見えるから。
そうやって解答用紙を埋めるのも大事。
しかし、(2)の問題は理屈が分かってないと気づけないのよ。
さて、どうやったら気づけるか。
天才的なひらめきなどは必要無い。
学んだことを引き出すだけ。
三角形の2辺の中点と中点を結んだ線分は、その下の底辺と平行になり長さは半分になる。
この中点連結定理を学んだ後に解く問題だから、ABとPQは平行、CDとQRも平行になる。
そこで、「平行」といえば中2で学んだ平行と角度を思い出す。
2直線が平行なら同位角と錯角が等しくなる。
そこから、与えられた条件と照らし合わせる。
∠ABD、∠BDC、2つの角度が分かってる。
その2つと同位角または錯角になる角度は無いか、注目するのは問われている∠PQRの部分・・・。
ここまでくれば高い確率で解き方に気づく。
「気づく」方法、それは学んだことを思い出す作業なのだ。
発想とは応用力などというものではない。
思い出す作業。
そのことを常に意識して問題を解くようにすれば、少しずつ問題の見え方が変わってくるよ。
↓ショート動画を続々更新中☆

このページに対してのコメント