小林多喜二の兄弟愛
塾で使用している中2の国語教材の中に、こんな文章がある。
小説「蟹工船」の作者として知られる小林多喜二の母が、息子たちのことについて語ったお話だ。
多喜二の家は貧しく、長男である多喜二だけが何とか親戚の援助で上の学校まで進学出来たのだが、弟の三吾は小学校までしか行けなかった。
ある日、学校の先生が弾いているバイオリンを多喜二と三吾が眺めていたところ、三吾があまりにも熱心に見つめていたので、先生が「弾いてみなさい」と言って貸してくれた。
一緒にいた多喜二は「弾けるわけがない」と思っていたが、なんと三吾は「サクラ サクラ」を一曲弾いてしまった。
「天才だ」という噂が広がったのだが、バイオリンは高価でとても買ってあげられないという両親の話を、多喜二は「ふーん」というくらいの感じで何となく聞いていたようだ。
その後、地元の銀行に勤めていた多喜二が初月給でバイオリンを買って家に帰ってきた。
さらに、ある学校の音楽の先生に三吾のバイオリンの先生になってくれるよう頼んできた。
多喜二は優しい兄だった。
どの兄弟にも荒々しい言葉は使わず、何でも静かに言って聞かせる兄だった。
多喜二が本を読んだり小説を書いている横で、三吾がバイオリンの練習をしていても「うるさい」など言ったこともない。
そんな多喜二が一度だけ三吾を叱ったことがあった。
ある日、三吾の練習するバイオリンの音を聞いた多喜二が「そこのところ、そんな音色でいいのか?」と聞きとがめた。
三吾が「いいんだ、本番の時はちゃんといい音色を出すから」と軽く答えた瞬間、多喜二が顔色を変えて怒った。
「練習で出せない音色がどうして本番で出せるのか、そんな態度ならバイオリンをやめてしまえ」と怒鳴った。
三吾は震えあがり、それからというもの、人がいようがいまいがバイオリンを手にしたら、本当に真剣に弾かなければ音楽に対して失礼なのだと身にしみて思ったという。
三吾はその後、東京交響楽団の第一バイオリン奏者になったそうな。
読みながら、じーんとくるお話であった。
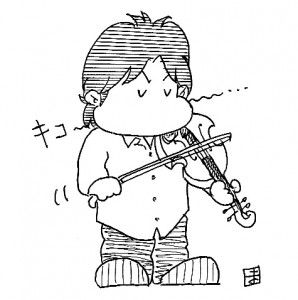

このページに対してのコメント




























